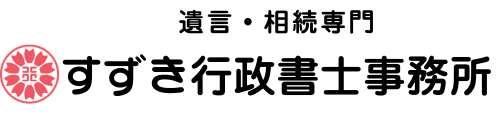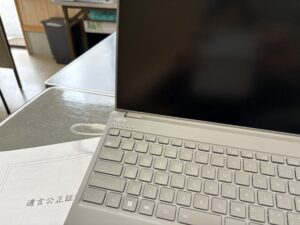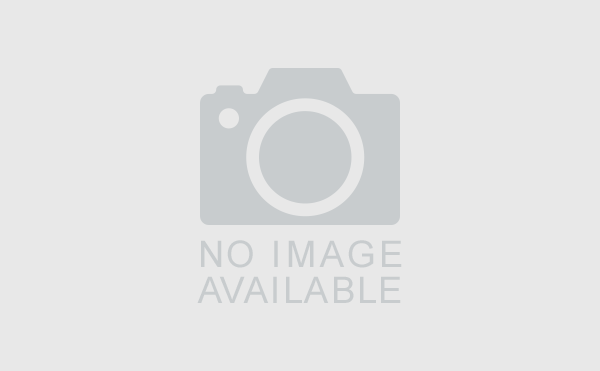孫夫婦に自宅を遺したい―施設入居後に作る遺言書の注意点
最近、80代の男性からこんな遺言書のご相談を受けました。
「介護施設に入ってもう家には住んでいません。今は孫夫婦がその家に住んでいます。長男と長女には預金を2分の1ずつ、自宅の土地と建物は孫に遺したいと思っています。」
長男・長女には公平に預金を分け、自宅に住んでくれる孫夫婦には家を継いでほしいというお気持ちです。
しかし、このような遺言を作る場合には、いくつかの注意点があります。
◆孫への遺贈は「相続人以外」への遺贈になる
まず押さえておきたいのは、孫は原則として相続人ではないという点です。
(※長男がすでに亡くなっている場合は代襲相続人になりますが、今回は長男が健在とします。)
そのため、孫に自宅を遺すことは「相続人以外の者への遺贈」にあたります。
この相談者さんは相続税はかかりませんが、相続税がかかる場合は次のような影響が生じます。
① 相続税が20%加算される
孫が遺産を受け取る場合、孫が支払う相続税には通常より20%の加算税がかかります。
孫への思いやりとして家を遺しても、税負担はやや重くなる点に注意が必要です。
② 基礎控除の人数に含まれない
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
孫は相続人ではないため、この人数に含まれません。
③小規模宅地等の特例が使えるかどうかの確認が重要
自宅の土地については、「小規模宅地等の特例」を使うことで、相続税の評価額を最大80%減らせる制度があります。 この特例を使えるかどうかで税額が大きく変わります。 孫夫婦が遺言者の自宅に同居していた場合など、条件を満たせばこの特例が使える可能性がありますが、 いくつかの細かい要件がありますし、度々改正もございます。 この判断は税務上非常に微妙なため、必ず税理士に確認・相談しておくことが大切です。
◆遺留分への配慮も忘れずに
長男と長女に預金を半分ずつ残す内容であっても、長男側の家系(孫)が多く受け取る形になります。 そうなると、長女が「不公平だ」と感じ、遺留分侵害額請求をしてくる可能性もあります。 事前に不動産の評価額を確認し、全体のバランスを考慮しておくことが重要です。
◆施設入居中に遺言を書くときのポイント
80代で施設入居中の場合、遺言書の有効性をめぐって「意思能力(判断力)」が疑われることがあります。 「誰かに言わされて書いたのでは?」というトラブルを避けるためにも、次の点を意識しましょう。
・公正証書遺言にする(公証人が本人の意思を確認して作成)
・医師の診断書を添付し、意思能力に問題がないことを証明する
・施設の職員や家族に作成の経緯を話しておく
こうした工夫により、「本人の確かな意思で作った遺言」であることを示すことができます。
◆まとめ
孫夫婦に自宅を遺贈するという遺言は、とても思いやりのこもった内容です。 しかし、孫が相続人でないことから、税金などで注意すべき点がいくつかあります。 これらを踏まえて、遺言者の思いを確実に実現するためには、法律と税務の両面からのサポートが欠かせません。 「孫に家を残したい」と考えたときは、まずは専門家に相談し、安心して実現できる方法を一緒に検討してみてください。