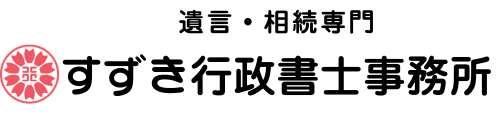事実婚でも安心して暮らすために知っておきたい遺言と年金のこと
遺言書というと「資産家の方が作るもの」というイメージを持たれる方も多いのですが、実際には次のような方に特におすすめです。
・子どもがいないご夫婦
・再婚で前妻や前夫との間に子どもがいる方
・相続人が多い、または疎遠な相続人がいる方
・相続人以外の人に財産を残したい方(事実婚のパートナーや友人など)
・自宅不動産や事業用の資産があり、スムーズに承継したい方
つまり「財産をめぐってトラブルになる可能性がある人」「自分の希望をしっかり反映させたい人」には、財産の多少に関わらず遺言書が大切になります。
事実婚パートナーに財産を残す遺言の注意点
事実婚のパートナーには法律上の相続権がありませんので、遺言がなければ財産を受け取ることはできません。だからこそ遺言書の作成が必要になります。
注意点としては次の通りです。
- 「遺贈する」と記載すること
相続人でない人に財産を渡す場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」とします。 - 遺留分に配慮すること
子や親がいれば、彼らに遺留分が認められます。全財産をパートナーに渡すと書いても、遺留分を請求される可能性があります。 - 遺言執行者の選び方
遺言を実際に手続きする人を「遺言執行者」といいます。パートナーを指定することもできますが、相続人と直接やり取りをする立場になってしまうため、感情的な対立が起きやすいです。そこで、専門家を遺言執行者にしておくと、間に立って公平に進めてもらえるので安心です。 - 公正証書遺言にすること
自筆では形式不備や紛失のリスクがあります。事実婚の場合は特に親族から争われやすいため、公証役場で作成する公正証書遺言が安全です。
死後事務委任契約について
財産の承継とは別に、「亡くなった後の生活の後片付け」を誰に任せるかも大事です。これをお願いできるのが「死後事務委任契約」です。
例えばこんなことを任せられます。
・葬儀や納骨の手続き
・病院や介護施設への支払い清算
・公共料金や家賃の解約手続き
・住居の片付け
事実婚のパートナーは法律上「遺族」ではないため、こうした手続きをスムーズにできないことがあります。死後事務委任契約を公正証書で結んでおくことで、安心して任せることができるでしょう。
年金はどうなる?
財産や生活に大きく関わる年金ですが、ここも注意が必要です。
公的年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は原則として法律婚の配偶者や子どもが対象で、事実婚のパートナーは対象外 です。
例外的に「婚姻と同様の実態がある」と認められれば受給できることもありますが、条件は厳しいのが実情です。
一方、企業年金や厚生年金基金などでは、規約によって事実婚のパートナーを遺族給付の対象としている場合があります。勤務先に確認してみるとよいでしょう。
年金で十分に備えられない分、生命保険や個人年金保険を活用して、確実に残せる仕組みを作っておくことが現実的な方法になりますね。
まとめ
事実婚のパートナーに財産を残したいと考えるなら、
・遺言書を公正証書で作る
・遺言執行者は専門家に依頼する
・死後事務委任契約も合わせて準備する
・年金の不足分は生命保険などでカバーする
このように複数の備えを組み合わせておくことで、もしもの時にも安心につながることでしょう。